医療保険がいらない理由とは?あなたが加入前に考えるべき5つの判断基準
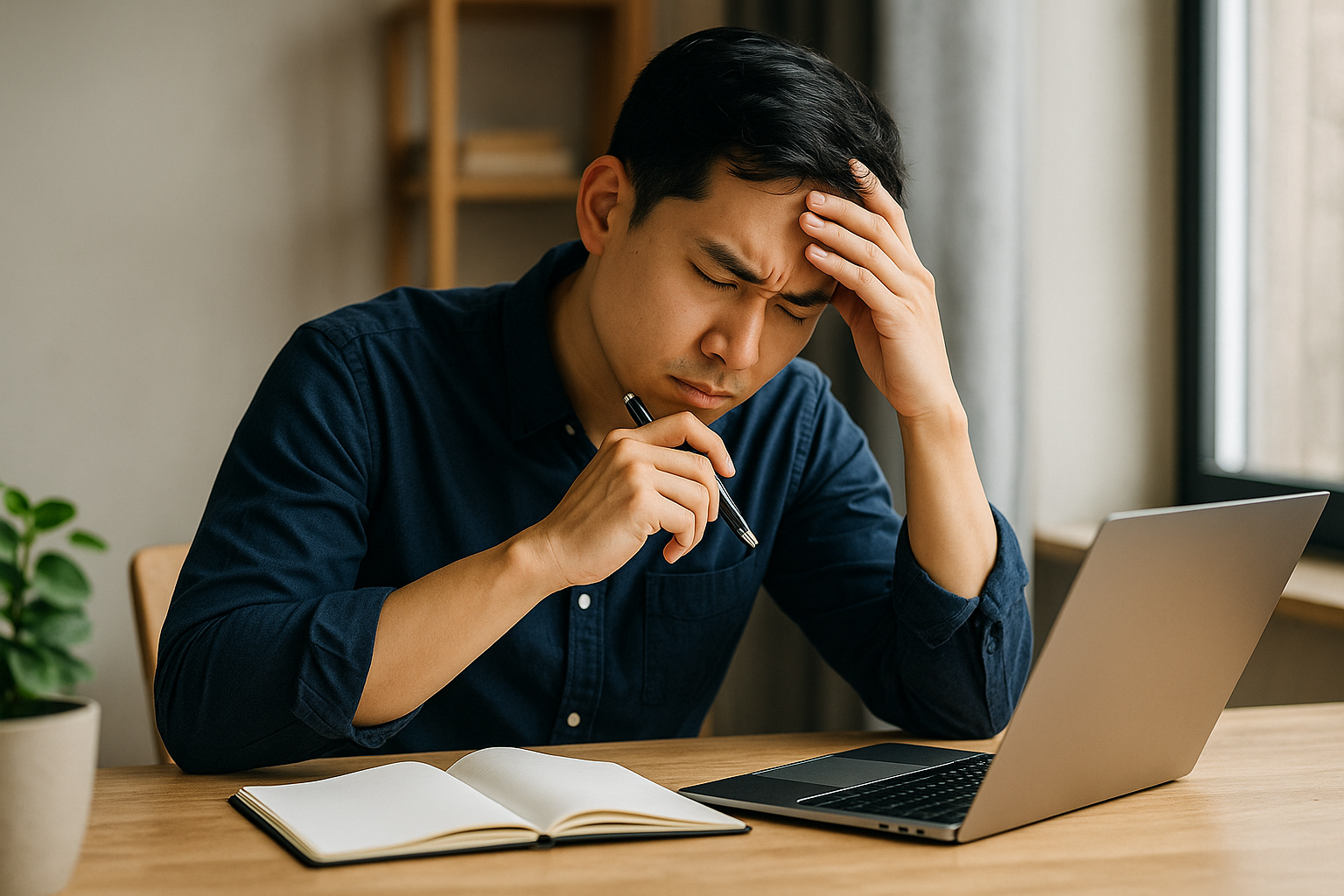

「医療保険って、本当に入らなきゃダメなの?」
そう思いながらも、なんとなく加入している方は多いのではないでしょうか。
「今は健康だから大丈夫」だけど「将来はどうなるかわからない」──この漠然とした不安を埋めるために、医療保険を選んでいる方も少なくありません。
特に、子育てや家計、ライフイベントに頭を悩ませながら、保険については誰かのすすめで決めた、というケースも多いはずです。
この記事では、そんな「なんとなく加入している」医療保険に対して、本当に必要かどうかを見直す視点をお届けします。
キーワードは医療保険がいらない理由──それは「将来に備える」という感覚を、違う角度から捉え直すことに他なりません。
医療保険を見直すことで、家計にゆとりを持たせたり、自分らしい生き方を選べる余地を広げたりすることができるかもしれません。
ただし、これは「絶対にいらない」と決めつける話ではありません。
この記事では「いらない」という考え方の根拠や背景を丁寧に紐解きながら、「自分にとって必要かどうか」を判断できるような材料を提示していきます。
読み終えるころには、あなたにとっての医療保険の必要性が明確になり、「あやふやなまま」だった不安がきっと薄れているはずです。
医療保険がいらない理由を 見直すべきタイミングとは

保険に加入するという決断は、多くの人にとって「万が一」に備えるための行動です。
しかし、保険のなかでも特に「医療保険」については、人生の中でどのタイミングで必要性を見直すべきかを意識する人は意外と少ないのが現状です。
例えば、以下のようなタイミングにおいては、一度立ち止まって医療保険がいらない理由を考える価値があります。
■就職・転職・独立時に見直す
社会人として初めて就職したタイミング、あるいは転職やフリーランスとして独立する際には、公的医療保険制度の変化が伴うことがあります。
会社員であれば厚生年金と健康保険がセットで整備されているため、病気、ケガでの入院や手術の際にも「傷病手当金」などで収入の補填が一定期間行われます。
一方、自営業、フリーになると、「国民健康保険」への加入が基本となり、保障内容が変わることになります。このとき、保障の内容と実際にかかる医療費とのバランスを再評価することが重要です。
■子どもが生まれたタイミング
子育てが始まると、教育費や生活費など出費が増える一方で、家計のバランスを見直す必要が出てきます。
この時期は、家族全体の保障をどう確保するかを考える良い機会でもあります。
医療保険に毎月数千円から数万円を支払い続けることが、将来的に本当に有効な備えとなるのかどうか──その点について、医療保険がいらない理由を軸に検討してみると、貯蓄や制度活用という選択肢が浮かび上がるかもしれません。
■健康状態が良好である時期
「健康である今だからこそ」こそ、冷静な判断ができるという側面もあります。
体調を崩してからでは、保険への加入が制限されることもありますが、一方で今の自分にとって本当に必要なのかという視点は、健康なうちでなければ持ちにくいのも事実です。
保険というのは、往々にして「何となく入っておいた方が安心」という心理で決められることが多いですが、それが必要以上の支出となっている可能性もあるのです。
■高額療養費制度や自己負担割合について理解できたとき
日本の公的医療制度は、自己負担が原則3割であるほか、「高額療養費制度」によって、医療費の自らの負担額が一定の金額を超えると、その超過分は支給対象となる制度が整っています。
例えば年収370万の会社員であれば、ひと月の医療費自己負担上限は約8万円前後。仮に100万円の入院費用がかかったとしても、実際に支払う額はかなり抑えられるのです。
この事実を理解した時点で、「医療保険がなくても制度でカバーできる」という現実に気づき、保険の加入目的を再評価したくなる方も多いでしょう。
■保険料負担が家計に響いていると感じた時
毎月の保険料が数千円〜数万円にのぼっている場合、それが家計を圧迫していないかを確認することも大切です。
固定費として長年にわたって支払い続ける金額は、トータルで見るとかなりの出費になります。
その金額を貯蓄に回したり、別のリスクに備えたりする方が効率的なケースも少なくありません。
このような見直しのタイミングでこそ、医療保険がいらない理由が具体的な意味を持ってくるのです。
このように、人生の各ステージに応じて、「医療保険は本当に必要なのか?」という問いを立て直すことは、将来の備えを賢く選ぶための第一歩となります。
見直しを通して、自分にとって最適な保障と支出のバランスを見つけることができれば、無駄な不安に縛られることなく、より自由な選択が可能になります。
医療保険 いらない理由は「健康保険制度の充実」にある

日本の医療制度は「国民皆保険制度」によって支えられており、全国民が何らかの公的医療保険に加入しています。この制度の最大の強みは、病気、ケガをした時に医療費用負担が大きく軽減される点にあります。この点を正しく理解することが、医療保険がいらない理由を考える上で非常に重要です。
■医療費の自己負担は原則3割に抑えられている
日本の公的医療保険制度では、医療機関で受ける診察、治療、手術、入院などの医療サービスの費用のうち、原則として3割だけを自己負担すれば済みます。
つまり、10万円の医療費がかかった場合でも、自己負担額は3万円に留まります(年齢や所得により負担割合は異なる)。
この3割負担の仕組みは、日常的な通院から高度な治療まで幅広く適用されるため、思ったよりも医療費の総額は抑えられるケースが多いのです。
これが、「医療費=全額自己負担」と誤解して医療保険に入ってしまうことが無駄になりうる理由の一つです。
■高額療養費制度で“高額”医療費もカバー可能
さらに注目すべき制度が「高額療養費制度」です。
これは、ひと月あたりの医療費が一定額をオーバーした時、そのオーバー分が払戻される制度です。
例えば、年収約370万円の人(標準の報酬月額が28万~50万円未満)であれば、1カ月の自己負担上限はおよそ8万~9万円。
仮に心臓の手術などで100万円以上の医療費がかかったとしても、自己負担額はこの上限を超えることはありません。
また、この制度は入院・通院問わず適用され、同一世帯で複数人が医療費を支払っている場合、合算もできます。
つまり、万が一の大病にも、公的制度だけで相当程度までカバーできるのです。
■会社員には「傷病手当金」制度もある
会社員や公務員が加入する健康保険には、「傷病手当金」という制度も用意されています。
これは、業務外のケガや病気で働けなくなった場合、給料の約3分の2が最長1年6カ月支給されるというものです。
たとえ収入が途絶えても、このような仕組みがあることで生活への影響を最小限に抑えることが可能となります。
そのため、「収入減に備えて医療保険が必要」と考えていた方にとっても、再検討の余地が生まれるでしょう。
■民間医療保険の役割を「公的制度」で代替できる
民間の医療保険は、入院給付金や手術給付金、通院保障などを備えていますが、実際にはこれらの給付がなくても日本の医療制度だけで十分にカバーされる場面が多々あります。
保険会社のパンフレットでは、保障内容が充実しているように見えますが、支給条件には制限があり、すべての治療や費用に対応できるわけではありません。
一方、公的制度は非常に広範囲に適用され、誰でも利用できるうえ、手続きさえ行えば確実に給付される信頼性の高い仕組みです。
これこそが医療保険がいらない理由の中でも最も大きなポイントだといえるでしょう。
■制度の正しい理解が“不要な保険”を見極める
医療保険の加入判断は、「何が心配か」ではなく「どこまでが制度でカバーされているか」の着目が大切なのです。
制度を知らないまま過剰に保険へ依存すると、不要な出費が続き、家計の無駄につながります。
そのため、「今、自分がどんな医療保障を受けることが可能なのか」「その制度で足りない部分は本当にあるのか」を一度丁寧に確認することが、保険加入の第一歩です。
これらの事実から、「医療保険がなくても安心できる状態」を作ることは現実的であり、むしろ公的制度の範囲内で収まる範囲ならば、民間保険の役割は限られたものであるといえます。
つまり、健康保険制度の充実こそが、医療保険がいらない理由の中核に位置するのです。
医療保険 いらない理由として「高額療養費制度」は見逃せない

医療費の支払いに関する不安の多くは、「もし大きな病気や手術で高額な医療費がかかったらどうしよう」という点に集中しています。
その不安を根底から覆す制度こそが「高額療養費制度」です。
この制度の存在を知るだけで、医療保険がいらない理由が一気に現実味を帯びてきます。
■高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、一か月に医療費が一定額を超えた場合、その超過分を健康保険から支給する仕組みです。
つまり、実際に支払う自己負担は「所得別の上限額」に抑えられるため、たとえ100万円以上の医療費がかかっても、すべてを自己負担する必要はありません。
この制度の基本的な構造は次のようになっています:
| 年収の目安(被保険者) | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 年収約370万円〜770万円 | 約8万〜9万円程度 |
| 年収約1160万円以上 | 約25万円程度 |
| 住民税非課税世帯 | 約3万5000円前後 |
このように、所得に応じて自己負担額が設定されており、高額な医療費が発生しても、上限を超える部分は払い戻されるのです。
■民間医療保険の想定リスクは「制度」でカバー可能
多くの民間医療保険では、「高額な入院費用が出たときの備え」として設計されています。
しかし、実際にはこの制度を活用すれば、予想していたよりも少ない金額の自己負担で済む可能性が非常に高くなります。
例えば、手術を含む入院で総額100万円以上かかった場合でも、実際の支払いは前述の通り8万〜9万円前後。
このような現実を踏まえると、月々の保険料を支払い続けることが本当に合理的かどうか、疑問が生じるはずです。
これが医療保険がいらない理由の中でも、多くの専門家が指摘する要素の一つです。
■「限度額適用認定証」を活用すれば窓口支払いも抑えられる
高額療養費制度は、通常一度全額を支払い、後日払い戻される形式です。
しかし、前もって「限度額適用認定証」を受領しておけば、最初から自己負担限度額までの金額しか支払わなくて済みます。
この制度を知らずに「とりあえず保険でカバーしよう」と考えるのは、大きな機会損失です。
認定証は、加入している健康保険組合や市区町村の窓口で簡単に申請でき、原則として数日以内に取得可能です。
■制度の対象範囲と注意点も理解しておこう
この制度は、原則、保険診療に対して適用されます。
なので、先進医療や自由診療、差額ベッド代や食事代といった「保険適用外の費用」は対象外です。
とはいえ、一般的な病気やケガの治療においては、公的医療の範囲内でカバーされることが大半です。
そのため、これらの費用が極端に高額になるケースはまれであり、ほとんどの入院・手術に関してはこの制度で十分に対応できます。
■高額療養費制度は年齢を問わず活用可能
この制度は、年齢や職業にかかわらず、すべての公的医療保険の被保険者に適用されます。
子育て世代はもちろん、フリーランスや自営業、派遣社員なども対象になります。
これにより、多くの人が同様の保障を受けられるという点でも、制度の平等性と信頼性が高いと言えるでしょう。
民間保険会社の医療保険に高額な保険料を支払う前に、まずはこの制度をしっかり理解し活用することが、合理的なお金の使い方です。
つまり、医療保険がいらない理由の中でも、この制度の理解と活用こそが最も効果的な「備え」となり得るのです。
医療保険 いらない理由の一つ「貯蓄でカバーできる範囲」について

医療保険に加入する最大の理由のひとつは、「急な出費に備えたい」という心理です。
確かに病気、ケガでの入院・手術などは予期せぬタイミングで発生し、多額の費用がかかることもあります。
しかし、こうした費用はすべてが莫大な金額というわけではなく、実はある程度の貯蓄があれば対応できるケースも多いのです。
そのため、「医療費=保険で備えるべき」という固定観念を見直すことが、医療保険がいらない理由の1つとして浮かび上がってきます。
■実際の入院費用はいくらかかるのか?
公益財団法人生命保険文化センターが調査したところ、入院1日あたりの自己負担費用(3割負担分)は平均で約2万円程度。
平均入院日数は11.9日とされており、単純計算で総額はおよそ24万円程度です。
この金額は決して安いとは言えませんが、「月1万円を2年積み立てていれば対応できる範囲」とも言えます。
つまり、医療保険に加入する代わりに、定期的に貯蓄をしておけば、十分に備えになるということです。
■貯蓄があれば保険料を支払わずに済む
月々数千円〜数万円の医療保険料を長期間支払うと、10年、20年でトータル100万円を超える支払いになることもあります。
一方、その保険料を自分で積み立てていくという選択肢もあります。
例えば、月1万円の保険料を20年間支払えば、合計で240万円。
これは、ほとんどの入院費や手術費用をカバーするのに十分な金額です。
しかも、保険と違って使い道は自由で、入院以外の生活費補填や教育費にも回すことができます。
これにより、医療保険がいらない理由は「支払い続けるだけの保険」ではなく、「自分で備える選択」の方が自由度も高く、経済的にも効率的であるという観点が見えてきます。
■「使わないかもしれない保険料」と「確実に使える貯金」
医療保険は、入院や手術をしなければ基本的に給付はありません。
つまり、「使わないかもしれないお金」を長年払い続けることになります。
一方、貯金であれば、病気をしなくても旅行、教育、老後資金などに転用可能です。
さらに、医療保険には「支払い条件」がつきもので、給付の対象外となる治療もあります。
そう考えると、「自分で管理できる資金」としての貯金の方が、リスクの幅が広くカバーできるという考え方も成り立ちます。
■貯蓄による安心感は精神的な余裕にもつながる
貯蓄があれば、病気やケガの際だけでなく、突然の失業、収入減、家族のトラブルなどにも対応できる可能性が高まります。
医療に限らず、生活全般のリスクを考える上で、流動性の高い資産があることは非常に大きな安心材料です。
また、貯蓄によって「保険を使わなければ損」という心理的なプレッシャーからも解放され、自分の判断で行動できる自由を手にすることができます。
■もちろん「貯蓄がない人」にはリスクもある
もちろん、すべての人が貯蓄を十分に持てるとは限りません。
収入が不安定だったり、急な出費が重なってしまう場合は、保険が精神的な支えになることもあります。
ただし、「根拠のない不安を理由に加入する」というのではなく、自分の収入や貯蓄状況を冷静に見直した上で、本当に必要かを判断することが重要です。
貯蓄があれば、短期的な医療費の支払いに困る可能性はかなり低くなります。
このような視点に立つと、医療保険がいらない理由は「制度でカバーできる部分は制度で、それ以外は自分で準備する」というバランスの取れた考え方へとつながっていくのです。
医療保険がいらない理由を考える上で「民間保険の限界」にも注目を

民間の医療保険は、CMや広告などで「万が一の安心」「入院1日につき◯千円支給」といった魅力的なコピーで広く知られています。
しかし実際には、そうした保障の多くが“思ったより使えない”ということも多くあります。
その理由を掘り下げてみると、医療保険がいらない理由の中でも、「民間保険の限界」を知ることが大きな判断材料になるとわかってきます。
■給付のハードルが高く「使えない」ケースが多い
民間医療保険では、入院や手術などの明確な条件が整わないと給付がされない仕組みになっています。
例えば、通院のみの場合、給付対象でないことが多く、短期入院や日帰り手術についても、保険会社ごとに対象の可否が異なります。
また、給付金の申請には診断書や証明書などの書類提出が求められ、その取得にも費用や時間がかかります。
「いざという時にすぐ使える」と思っていた保険が、実際にはハードルの高い手続きに阻まれてしまうこともあるのです。
■入院日数の短縮で「元が取れない」傾向に
現代の医療現場では、入院日数の短縮化が進んでおり、数日〜1週間程度の入院で済むケースが増えています。
ところが、保険の多くは「入院1日につき給付金〇円」という仕組みであり、入院日数が短いとその分支給額も少なくなります。
たとえば、3日間の入院で1日5,000円の給付金だとしても、合計は15,000円。
月々の保険料が5,000円なら、たった3カ月で支払額と給付額が逆転してしまいます。
このように、短期入院が主流となった現代医療では、民間医療保険のコストパフォーマンスが著しく下がっているという現実があります。
それは医療保険がいらない理由として、合理的な根拠になりうるのです。
■「先進医療特約」なども過信は禁物
一部の民間保険には、「先進医療特約」や「自由診療対応」などの付加保障がついています。
確かに、保険適用外の高額医療への備えとしては魅力的に見えますが、実際にそのような先進医療を施される可能性は極めて低いという統計もあります。
さらに、先進医療の実施件数は限られており、実際に希望しても受けられないことがあるため、月々の保険料にそれだけの価値があるかどうかは慎重に見極める必要があります。
■保障内容の複雑さが“理解しづらさ”に繋がる
保険のパンフレットや公式サイトを見ると、細かい条件や例外規定が無数に記載されており、読み解くのも一苦労です。
そして、保障内容をしっかり理解しないまま加入してしまい、「いざというときに適用外だった」というケースは多々あります。
このような「わかりにくさ」こそが、民間医療保険の限界であり、情報格差によって損をしてしまうリスクを孕んでいます。
■「安心」のために支払うコストが高すぎることも
多くの人が医療保険に求めているのは「安心感」ですが、その安心感に対するコストが妥当であるかは、冷静に考える必要があります。
保険料を10年、20年と支払うことは、何十万円もの出費になります。
それに対して、得られる給付は「病気になったときに限り」「一定の条件下でのみ」という限定的なものです。
このバランスの悪さに気づいたとき、初めて医療保険がいらない理由に対する理解が深まるのではないでしょうか。
民間保険の存在を否定はしませんが、その限界やデメリットを把握した上で判断することが重要です。
必要以上に不安を煽られたり、広告だけで判断してしまうのではなく、現実に即した保障内容と自分の生活状況を照らし合わせることが、賢い選択への第一歩です。
医療保険 いらない理由を踏まえた「保険料と家計のバランス」の考え方
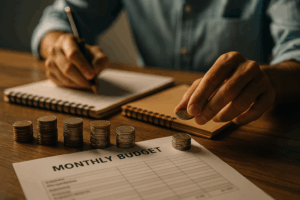
医療保険に加入している方の多くが見落としがちなのが、「毎月支払っている保険料が家計にどの程度の影響を与えているか」という点です。
生活にゆとりがあるときは、あまり気にはならないと思いますが、教育費や住宅ローン、食費の高騰など、家庭を取り巻く経済環境は年々厳しさを増しています。
その中で保険料が占める割合を可視化してみると、医療保険がいらない理由が家計の視点からも見えてくるのです。
■月々の保険料を家計全体で見たときの影響
たとえば、民間の医療保険に月5,000円支払っているとします。年間では60,000円、10年間で600,000円です。
これを「保険に回す余裕がある金額」と見るか、「家計を圧迫する固定費」と見るかで、判断は大きく変わります。
家計の中で見直しやすい支出といえば、通信費や食費が代表的ですが、保険料も見直しても良い“固定費”の一つです。
むしろ、自動引き落としで「気づかずに払っている」性質を考えると、見直しの優先度は非常に高いと言えます。
■保険料と「何に備えているか」の不一致
医療保険に加入している人の中には、「とりあえず何かあったときのため」という漠然とした不安を動機としているケースが多くあります。
しかし、その不安が何なのか明確にできないまま支払い続けていると、支出に対する効果が非常にあいまいになります。
例えば、「入院したら困るから備える」というのであれば、公的な医療保険や高額療養費制度、貯蓄など、他の選択肢で対応できることを知るだけでも、医療保険がいらない理由が具体的に理解できるようになります。
■医療保険にかけていた費用で「他のリスク」に備える選択
医療保険にかかる月額5,000円を、もし別の目的に振り分けたらどうなるでしょうか。
例1:子どもの教育資金に月5,000円を積み立てる
例2:家計全体の緊急時用貯蓄に回す
例3:老後の生活費・介護費用のために長期運用
このように、将来起こる可能性が高い「他のリスク」に備えることも、家計全体で見たときには有効な判断です。
特に貯蓄や資産形成は、医療以外のリスクにも幅広く対応できるため、より柔軟性の高い選択と言えるでしょう。
■「節約」ではなく「見直し」という発想を
保険料を削るというと、生活の質を下げる「節約」として捉えがちですが、本質はそうではありません。
「本当に必要な保障を見極めた結果、不要な支出をなくす」という行動は、家計の健全化と生活の自由度を高めるポジティブな戦略です。
実際、保険料の見直しによって年間10万円以上の支出が軽減される家庭もあり、その分を旅行、教育、老後資金など、自分たちの価値観に沿った使い方へと転換することが可能になります。
■家計の「固定費」は定期的に見直すのが鉄則
携帯料金や光熱費は時代の変化とともにプランが変わり、定期的に見直すのが常識となりつつあります。
同じように、保険もまた「一度加入したら終わり」ではなく、生活状況の変化に応じて再評価すべき支出です。
・子どもが生まれた
・収入が増減した
・転職や独立をした
・病気やケガに対する価値観が変わった
こういった変化があったタイミングで、「このまま保険を続けるべきか?」という問いを立て直してみることで、医療保険 いらない理由がご自身の現状とどう関係しているかが見えてきます。
家計の安定と自由を守るためには、「なんとなくの保険加入」を見直し、保険料という“固定費”を自分の価値観に合った形で最適化することが求められます。
そうすることで、本当に必要な備えに集中でき、家計全体にゆとりと安心が生まれるのです。
医療保険 いらない理由に当てはまらない「例外ケース」も存在する

ここまで見てきたように、医療保険がいらない理由には多くの合理的な根拠があります。
公的な医療保険制度の充実、高額療養費制度、貯蓄による備え、そして保険料と家計のバランス──これらを踏まえれば、「民間の医療保険は不要では?」と感じる方も多いでしょう。
しかし、すべての人にとって医療保険が不要かというと、必ずしもそうとは言い切れません。
ここでは、医療保険が「例外的に有効に機能するケース」について紹介します。
これらに該当する方は、慎重な判断が必要です。
■慢性的な持病がある、または高リスク群に属する人
糖尿病、心疾患、腎疾患など、治療や通院が継続的に必要な慢性疾患を抱えている人にとっては、医療費の負担は想像以上に大きくなります。
特に、入退院を繰り返すようなケースでは、高額療養費制度の上限に達しない範囲でも、自己負担額の積み重ねが家計に響いてきます。
また、がん家系である、特定の遺伝疾患リスクがあるなど、「将来高確率で医療が必要になる可能性がある人」にとっては、医療保険が“コスト以上の安心材料”になる場合もあります。
■貯蓄が少なく、急な出費に対応できない場合
医療費の支払いは、たとえ制度でカバーされるとしても、一時的には自己負担が発生します。
たとえば、高額療養費制度の払い戻しは後日になるため、いったん立て替える資金が必要です。
この「一時的なキャッシュ不足」に耐えられない家庭にとっては、医療保険の給付金が非常にありがたい存在となるでしょう。
特に、シングルマザーや非正規雇用などで収入が不安定な方は、「貯蓄ではカバーできない突発的支出」への備えとして医療保険を活用する選択も現実的です。
■精神的な安心感を重視するタイプの人
合理的な損得だけではなく、「何かあったときにお金が出る」という“精神的な安心”があることで、普段の生活に落ち着きが生まれる人もいます。
このような人にとって、保険料の支払いは「保険という商品を買っている」のではなく、「安心感を買っている」と言えるかもしれません。
もちろん、月々の支出とのバランスを見極める必要はありますが、精神的な側面も含めた「ライフスタイルの一部」として医療保険を考えるのは、一つの考え方です。
■出産・育児を控える女性
女性にとって特に注意が必要なのが、出産や育児に伴う医療リスクです。
妊娠中のトラブルや出産に伴う異常、帝王切開などによる入院・手術のケースでは、医療費が想定外にかかってしまいます。
また、妊娠が判明した後では新規加入ができない保険商品も多く、出産前の計画的な加入が必要になります。
女性特有の医療ニーズに応じた保険は、「医療保険がいらない」という一般論ではカバーできない領域です。
■地方在住や医療機関へのアクセスが限られる人
都市部と比べて医療機関へのアクセスが限られる地域では、自由診療や差額ベッド代など、想定外の費用が発生しやすくなります。
また、地域によっては「紹介状がないと受診できない」「緊急時の搬送に費用がかかる」など、追加コストの発生リスクもあります。
そうした環境下では、医療保険の給付金が「予備費」として大きな意味を持つことがあります。
■フリーランスや自営業で収入が不安定な人
厚生年金や傷病手当金のような保障が受けられない自営業・フリーであれば、病気やケガで働けなくなると収入が一気にゼロになります。
このような職業形態の方にとっては、入院給付金だけでなく、就業不能保険や生活費補填の役割も持つ医療保険が心強い存在になります。
「働けない=収入ゼロ」になるリスクが常にある人にとって、医療保険は“収入の保険”でもあるのです。
このように、医療保険がいらない理由が多数存在する一方で、すべての人がそのまま当てはまるわけではありません。
自身の健康状態、家計状況、ライフスタイル、職業、住環境など、様々な要素を考えた上で、「自分にとっての最適な選択」を見極めることが大切です。
医療保険がいらない理由を理解したうえで考える「備え方の選択肢」

ここまでで、医療保険がいらない理由には十分な根拠があることを見てきました。
しかし、「じゃあ、何も備えなくていいの?」と問われれば、それもまた違う答えになります。
医療保険が不要かもしれないと判断できたとしても、リスクに備えること自体は必要です。
重要なのは「保険に入るか・入らないか」ではなく、どんな形で備えるかを選べる立場にあるということ。
ここでは、医療保険以外の“現実的かつ有効な備え方の選択肢”を紹介します。
■選択肢①:医療費専用の貯蓄口座を作る
まずはもっともシンプルかつ再現性の高い方法として、「医療費専用の貯蓄」を行うことが挙げられます。
これは、いわば“自分専用の保険”を構築するようなものです。
月々1万円を貯蓄しておけば、年間12万円
5年で60万円、10年で120万円
一般的な入院費用(数万円〜30万円)に十分対応できる額
この資金は、医療に使わなければ他の目的(教育費、老後資金)にも回せるため、柔軟性があります。
また、使わなければ資産として残り、使っても給付条件や審査に縛られず即時対応できるという点で非常に実用的です。
■選択肢②:掛け捨てではない「積立型保険」の活用
もしも「どうしても保険という形で備えたい」という人には、掛け捨て型ではなく、貯蓄性のある積立型保険も選択肢の一つです。
ただし、利回りや元本割れのリスク、保険会社の信頼性などを十分に比較検討する必要があります。
「保障」と「資産形成」の両方を意識したい場合には、学資保険や終身保険をベースに必要最低限の医療特約を付けるという方法もあります。
■選択肢③:共済などシンプルな保障商品を選ぶ
共済(生協やJAの提供する保障)は、保険会社の医療保険と比べて掛金が安く、保障内容もシンプルでわかりやすいのが特徴です。
最低限、必要となる保障を、割安な価格で確保したい方には適した選択肢となります。
特に、医療保険に「万が一に備える」程度の役割を求める人にとっては、コストパフォーマンスが非常に高い商品と言えるでしょう。
■選択肢④:高額療養費制度+短期生活資金の備えを整える
公的医療保険の自己負担額は高くても月8万円〜10万円前後(所得により変動)。
この水準を支払える「短期のキャッシュ」があれば、十分にリスクを回避できます。
この考え方は、まさに医療保険がいらない理由を実践に落とし込んだ形です。
・高額療養費制度:自己負担を抑える制度
・傷病手当金:会社員の休業時の生活保障
・短期貯蓄:一時的支出に対応するキャッシュ
これらを複合的に活用すれば、民間医療保険に頼らずとも高い水準のリスク管理が可能です。
■選択肢⑤:「保険よりも収入の仕組み」を整える
医療保険は「支出を防ぐ」ためのものですが、別の視点として「収入を守る・増やす」仕組みを持つという考え方もあります。
・不労所得(投資・配当)をつくる
・副業で収入の柱を増やす
・働けなくなった場合の収入減対策として、就業不能保険を検討する
このように、“リスクを収入で吸収する”発想は、現代的なライフスタイルにも合致しています。
■最も大切なのは「自分で選ぶ」ということ
これらの選択肢を見てわかる通り、医療保険に頼らなくてもできる備えは複数あります。
重要なのは、「保険に入っているから安心」ではなく、「自分にとってどの備えが最適かを自分で判断できる」ことです。
情報を知り、自分の家計や健康状態、生活環境と照らし合わせて考えることで、はじめて選択肢の幅が広がります。
つまり、医療保険がいらない理由を理解した先にこそ、本当に自分に合った備え方が見えてくるのです。
それは“保険に頼らない”という選択肢を持てることの自由さであり、そして、最も合理的なリスク管理とも言えるでしょう。
医療保険がいらない理由を信じても「将来不安」が残る人の対処法

ここまでの記事を読んで、「なるほど、医療保険がいらない理由には一理ある」と思ってくださった方もいるかもしれません。
しかし同時に、「でも、やっぱり将来が不安…」「いざというとき、本当に大丈夫なのか」と、どこか心の奥に残る“漠然とした不安”を拭いきれない方もいるのではないでしょうか。
これは非常に自然な感情です。
不安が完全になくならないからこそ、保険は存在し続けているとも言えます。
ここでは、そのような「理屈では納得しているけれど、不安は残る」という方に向けて、具体的な対処法をご紹介します。
■「不安の正体」を紙に書き出して言語化する
不安の多くは、頭の中で漠然と渦巻いているだけで、実態をつかめていないことが多いです。
まずは、どんな不安を感じているのかを紙に書き出してみてください。
・自分や家族が入院したらどうしよう
・手術費用が払えなかったら
・働けなくなったら収入が途絶えるかも
・一人暮らしだから、倒れたときが怖い
このように書き出すことで、「それは保険でしか対応できないのか?」「制度や貯蓄でも備えられるのか?」という冷静な視点を持つことができます。
■「シミュレーション」をしてみる
次におすすめなのが、実際に入院や手術が起きたときの費用シミュレーションを行うことです。
・年収400万円の会社員が7日間入院+10万円の手術を受けた場合
医療費総額:約40万円
自己負担額(3割):約12万円
高額療養費制度適用後の自己負担:およそ8万円前後
この程度の支出であれば、貯蓄や医療費専用口座で十分対応可能だと分かるはずです。
漠然とした不安は、「現実的な数字」として可視化することで薄れていきます。
■「万が一」の定義を明確にする
「万が一に備えたい」という言葉は、便利なようで曖昧です。
何をもって“万が一”とするのか、どこまでを想定しているのかを明確にしましょう。
・数日〜1週間の入院
・大手術を伴う長期療養
・難病やがんなど長期治療が必要なケース
この中で、どの程度まで備える必要があるかを冷静に考えれば、「このケースだけは不安だから備えよう」「ここまでは公的制度で十分」といった線引きができるようになります。
■「全部を保険で解決しようとしない」こと
医療保険であれ、生命保険であれ、どんな商品も万能ではありません。
実際には、保険・制度・貯蓄・収入といった複数の要素を組み合わせて備えるのが理想的です。
むしろ、保険だけに頼ると「保険が適用されないと困る」「条件外だったらどうしよう」という新たな不安を抱えることにもなりかねません。
だからこそ、医療保険がいらない理由を理解した人こそ、「全部を保険で解決するのではなく、分散して備える」考え方に切り替えることが大切なのです。
■「選択する自由」を実感すること
情報を得て、自分にとって不要かもしれないと判断し、別の形で備える。
この一連のプロセス自体が、“自分の人生を自分で選ぶ”という行動です。
将来への不安を「消す」のではなく、「対応可能な不安に変える」こと。
それが、本当の意味での備えであり、納得感を持って生きていくための力になります。
不安が完全に消えなくても大丈夫です。
不安を直視し、対処法を持っておくこと自体が、最も有効な「安心」につながります。
医療保険がいらない理由を信じてもなお残る不安があるなら、その不安を受け入れつつ、“自分なりの備え方”を見つけることが、真に価値ある選択です。
医療保険 いらない理由を総まとめ|加入・非加入の判断基準とは

ここまで、医療保険について深く掘り下げながら、医療保険がいらない理由を様々な視点から解説してきました。
その中で見えてきたのは、「医療保険=必ず必要」という前提が、実は思い込みに過ぎない可能性があるということ。
そして、医療保険が必要かどうかは、「自分にとっての備え方」をどう設計するかにかかっているという結論です。
このまとめパートでは、これまでの内容を振り返りながら、「自分は医療保険に入るべきか否か」の判断軸を整理しておきましょう。
■医療保険 いらない理由の主な根拠
・日本の健康保険制度が優秀
自己負担は原則3割、高額療養費制度もあり、想像以上に公的支援が充実しています。
・高額療養費制度により“高額な出費”は抑えられる
年収に応じて自己負担上限が設けられており、入院や手術があっても費用が跳ね上がることは少ないです。
・貯蓄で十分に備えられる
短期入院など多くの医療支出は、貯金でカバーできる範囲に収まることが大半です。
・民間医療保険の給付条件が厳しく、元が取れない可能性がある
特に入院期間が短縮化傾向の現代では、給付額より支払う保険料の方が高くつくことも。
・家計を見直すと、保険料の削減が有効な支出圧縮策になる
固定費として継続的に発生する保険料を、貯蓄、投資に用いる方が合理的な場合があります。
■一方で医療保険が必要になる「例外ケース」もある
すべての人にとって医療保険が不要かというと、そうではありません。
以下に該当する人は、医療保険の検討が有効な場合もあります。
・慢性疾患などで継続的な通院・入院が予想される人
・貯蓄がなく、急な出費に対応できない人
・精神的な安心を保険に求めている人
・出産・育児リスクに備えたい女性
・医療機関へのアクセスが限定される地方在住者
・フリーランスや自営業など、収入が不安定な職業の人
■判断基準は「自分のライフスタイル×リスク許容度」
医療保険がいるかいらないかの判断は、結局のところ「自分自身のライフスタイル」と「どこまでリスクを受け入れられるか」によって変わります。
✔️ 加入した方がよい可能性が高い人
・万が一の医療費に対する備えがなく、貯蓄も不十分
・心配性で、給付金がないと精神的に落ち着かない
・働けなくなった際の生活費に不安がある
✔️ 非加入でも問題ない可能性が高い人
・公的制度の知識があり、活用方法も把握している
・貯蓄が一定額あり、医療費への備えも意識できている
・家計を圧迫する保険料の支払いより、資産形成に興味がある
■“備える”ということの本質を見直す
保険とはあくまで、リスクを「金銭でカバーする手段の一つ」です。
それが医療保険であっても、他の備え方であっても、自分が納得し、実行可能な形で準備できていれば問題はありません。
不安を埋めることが目的ではなく、不安に対処できる準備があること──それこそが、本当の意味での「安心」といえるかもしれません。
■最後に:選択肢は「加入」か「非加入」だけではない
実際には、「最低限の保障だけを持つ」「医療保険はやめてがん保険だけ残す」「貯蓄と制度でバランスを取る」など、さまざまな折衷案があります。
二者択一に縛られず、自分にとってベストな備えを組み合わせることが、これからの時代には求められる力です。
そして、あなたが今こうして「本当に医療保険は必要か?」と疑問を持ち、調べ、学んだこと自体が、すでに最初の一歩となっています。







